iLikeは米国で人気爆発な音楽コミュニティサービスである。
mixiミュージックを10倍くらい洗練させて、試聴(45秒)機能を提供し、ソーシャルなリコメンドによってユーザと曲をマッチさせるサービスだ。
iTunesで視聴した曲の情報をアップしてという部分はmixiミュージックも同じだがシンプルさが段違いである。またiLikeの場合、「iLike sidebar」というiTunesに組み込むタイプのプラグインが用意されており、iTunesで曲を聴くだけでその曲をキーとしたリコメンドを表示し、試聴が可能になっている。言葉で説明すると難しそうだが非常にシンプルなサービスである。
具体的に説明しよう。
例えば、上記、iTunesでは「Yo-Yo Ma」の「Fugata」が再生されている。

するとiTunesのサイドバーにこのような画面が表示される。
この画面、何かというとYo-Yo Maに関連してそうな曲をリコメンドしてくれているのである。

曲名の左脇についているブルーの再生ボタンを押すと各曲を試聴することができる。

リスナー同士のつながりもしっかりとサポートされており、最下段には同じ楽曲を再生したユーザが表示されている。

しかしiLikeの本来の目的は中段に表示されている「Download free MP3s from new artists」によって提供される「チャートでは見つけることができない新しいアーティストとの出会い」である。
この点については現在、日本からはアクセスできなくなっている音楽遺伝子によるリコメンデーションサービスである「Pandora」も同じで、どちらのサービスもその本来の目的は「表にでることができないでいるアーティストとリスナーの幸福なマッチングによる音楽マーケットの活性化」なのである。
両サービスともに試聴によってメジューな音楽を聴く機会も提供している。(Pandoraはインターネットとしてフル視聴をサービスしていたのだが米国内の法律改正の為、現在は日本からのアクセスを閉ざしている)
こうした試聴の自由化は日本ではほとんど進んでいない。英語圏でこの種のサービスが可能なのはナップスターショックで法整備が進んだことが理由だ。
これは「経済的な有効性を考えるとまずは音楽を届ける環境をつくる。マネタイズはその後で考える。その方が合理的」という考え方に基づく。日本と英語圏のサービスとでは差は開くばかりで、もはや追いつくことは不可能であろう。よって、彼らとは別な方向性を提示する以外の選択肢はないと考えるべきである。
FacebookでもNo.1人気アプリなiLikeなのだが日本ではほとんど認知されていない。
しかし、このiLikeがとうとう日本でも注目されるかもしれない。
それが表題にも提示した「U2の未発表曲がiLikeで公開される」という事件である。
詳しくはTechCrunchの下記の記事を参照して欲しい。
早速、視聴してみたがこの視聴感覚は新鮮である。
日本であればTVなどのマスメディア以外では公開されないであろう映像だ。(最も合理的に考えれば日本ではその方が効果的だが。話はそれるが先日の中田の旅先でのインタビューなどTBSではなくYoutubeかustream.tvでdotsubを用いたマルチリンガル環境で公開されるべきである)
下記、U2のBonoが新曲「Wave of sorrow」の由来についてiLikeの創設者に語ったインタビュー映像である。
ビデオ中盤からは楽曲が視聴できる。
映像はビデオカメラで録画されたものだろう。
カメラは一台でアングルも固定である。
いたって普通の映像なのだがこれがオンラインのしかもYahoo!などに比べれば遥かにマイナーであろう、iLikeで公開されているというコンテクストが強烈に映像を面白くしている。(もちろん、Bonoの存在が最大の要因なのだが)
これこそコンテンツパワーと呼ぶべき映像だと僕は思う。
お茶を濁す程度のCGMによるコマーシャルの作成は全く本質的な変化にはつながっていない。
既存の素人参加型プロモーションがカタチを変えたにすぎない。
ペイパーポストによるブログプロモーションも同じである。
コンテクスト、クオリティともに既存のプロモーション手法をネットに置き換えたにすぎない。
そこからは変化は生まれない。
Bonoの映像をみながらそう思った。
++++++
迷うことは多々あるのだが
「迷ったら、神のようにふるまいなさい」(マドンナ)
というのがひとつの答えではないかと思う。


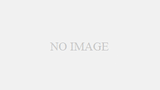
コメント